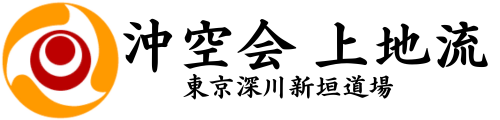上地流
Uechi-Ryu
上地流空手は、創始者・上地完文(うえち かんぶん)師によって体系化された沖縄発祥の武道であり、中国南派少林拳の流れを汲む独自の空手流派です。完文師は19世紀末から20世紀初頭にかけて中国福建省に渡り、厳しい修行を通じて拳法の奥義を学び、その教えを基盤として帰国後、沖縄で上地流を創始しました。単なる格闘技ではなく、「術(技)」と「道(精神)」の一致を重んじ、心身の統一を目的とした総合的な修養体系として構築されています。
上地流の教えは、「理(ことわり)」と「業(わざ)」の両立にあります。理とは武道の根本原理であり、業とはその原理を体現する実践の技です。理に基づかない技は暴力に過ぎず、業の伴わない理は空論に過ぎない――その両者を一体として修めることが上地流の根本理念です。この哲学は、剣道や柔術など他武道の理論体系とも共鳴しつつ、上地流特有の「心身一如」の境地を追求しています。
上地流の稽古体系は、基本型「三戦(サンチン)」を中心に、補助運動、型の体系、応用の体系、そして自由組手へと段階的に構成されています。三戦の型は呼吸と姿勢を通して身体と精神を統一する基礎であり、これを通して心身の安定と力の制御を学びます。補助運動や約束組手では、理合を理解しつつ動作を磨き、やがて自由組手(無防試合)において、実戦と心の平常を両立させる段階へと進みます。
特に「自由組手」は、上地流の最終段階として重要な意味を持ちます。それは敵を倒すための闘争ではなく、自らの内にある恐れや執着を制する試練の場です。攻防は一体であり、自己防衛の極意は「攻撃の中に防御を見出す」ことにあると説かれています。上地流における“自由”とは、無秩序ではなく、理に基づいた自由、すなわち己の心と身体を完全に制御する境地を指します。
上地流空手は、その誕生以来、沖縄武道の精神と中国武術の理論を融合し、時代を超えて受け継がれてきました。上地完文師の志は、弟子である上地完英師によって体系化され、今日の上地流空手道として世界中に広がっています。その根底にあるのは「平和を志向する武の哲学」。戦わずして勝つ、そして己を磨くための道として、上地流空手は今も多くの人々に深い学びと気づきを与え続けています。